生前対策(贈与・遺言)・民事信託
こんなお悩みありませんか?
将来残される人のために準備をしておきたい。
不動産を贈与したいがどうすれば良いのかわからない。
遺言書を書きたいがどうするのが良いのかわからない。
最後に自分の財産をどうするのか決めておきたい。
子供がいないため自分の財産がどうなってしまうのか不安。
何も準備していないと、遺産相続で相続人同士の争いが生じる事や、相続税の準備をしていなかったなど、様々な問題が生じてきます。
相続で争わない、もめないためには事前に準備することが必要です。
円満な相続を行うために今のうちから生前対策をお薦めします。
遺言作成

最近、遺言書を残される方が増加しております。
しかし、遺言書で、法的拘束力のあるものを作成するには、きちんとした手順をとる必要があります。
当事務所ではわかりやすく遺言書の作成のアドバイスや、原案の作成を行っております。
お気軽にご連絡下さい。
贈与

生きている間に財産を他人に譲ることを「生前贈与」と言います。
相続税の納税額そのものを減らすことができるのでとても効果的です。
しかし、やり方を間違えてしまうと相続税よりも高い贈与税を払うことになってしまうということがございますので、専門家にお任せ下さい。
※税金の専門家である税理士と協力しながら最善の方法をご提案致します。
民事信託

民事信託は比較的新しい制度です。
信託とは、依頼された方が、依頼した方から、依頼した方の財産(信託財産)を、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度のことです。
「信託」と聞くと投資信託を思い浮かべる方が多いかもしれません。
民事信託は、投資信託とは全く異なります。
財産の管理を家族や親族に任せることが目的です。
見積もり相談無料。お気軽にご相談を!
無料相談
ご相談者様が安心してご相談できるよう相談は無料です。
土日祝・時間外対応
時間外のご相談も事前にご予約いただければ対応致します。
駐車場完備
事務所前に駐車場3台完備。富士宮市役所から徒歩4分です。
出張相談
ご希望の方には出張、リモート相談も可能な場合があります。
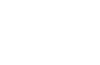 無料相談・お問い合わせ
無料相談・お問い合わせ